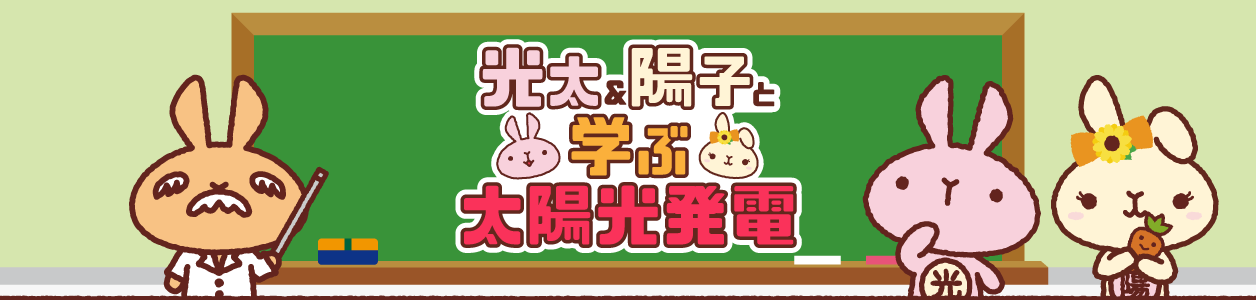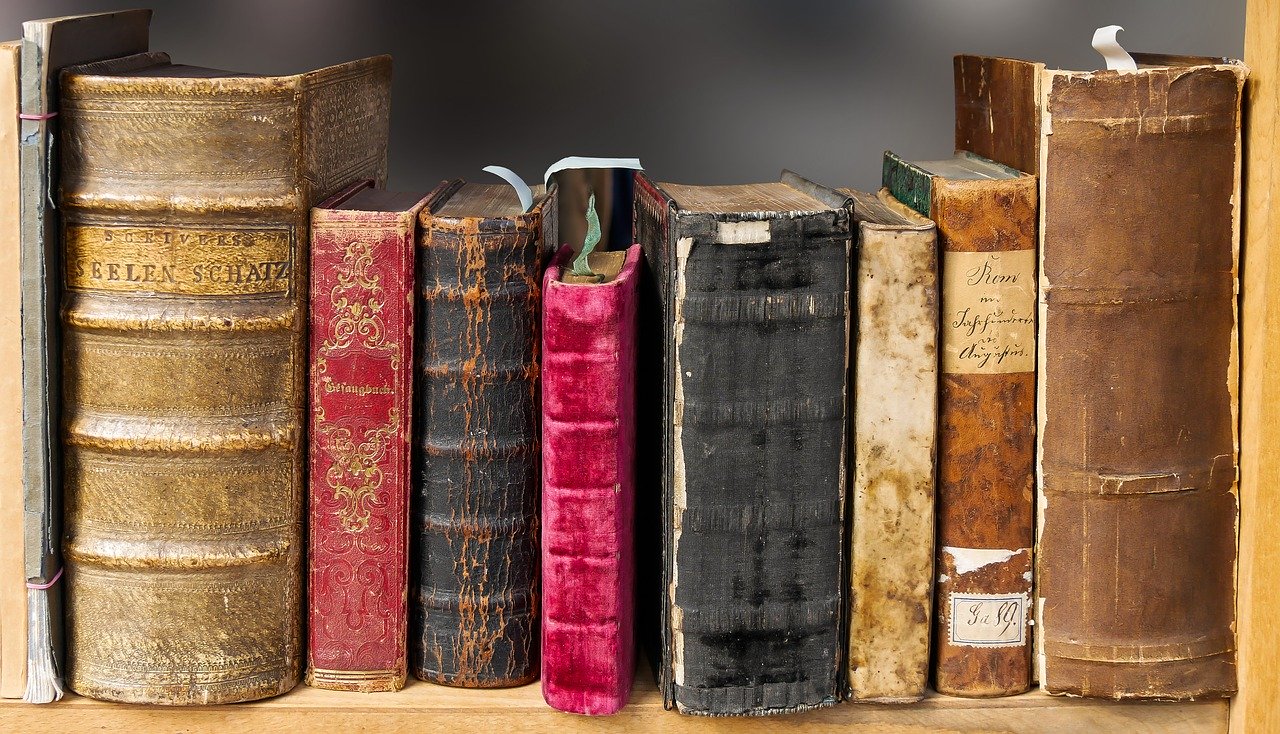ねえねえ陽子ちゃん。太陽光発電ってさ、太陽の光で発電するんだよね!

当たり前じゃない!急にどうしたの?

なんだかそれって、よく考えたら未来っぽくてかっこいいなあと思ってさ!

また変なこと言って…!でも、その気持ちはちょっと分かるかも。
宇宙から届く光で電気を作るって、なんだかロマンチックだよね!

ほうほう。お二人さん、中々面白い話をしとるのう。

あっ博士!太陽光発電ってすごく未来を感じるなあって思ったんだけど、一体いつ頃発明されたのかな?ここ最近?

フフフ、それはじゃのう…

そ、それは…!?

そ、それは…!?

続きは目次の後じゃ!
太陽光発電システムはこうして生まれた!
世界で初めて開発されたのは〇〇年前!?

実は、太陽光発電システムに欠かせない太陽電池が世界で初めて発明されたのは、
今から60年以上も前のことなんじゃ。

ろろろろ、ろくじゅうねん!?

想像していたよりもずっと昔に発明されていたんだね!

1954年にアメリカの研究施設で開発された世界初の太陽電池は、それから4年後の1958年には人工衛星に搭載されたんじゃ。
そして、それは太陽電池にとっての初仕事でもあったんじゃよ。

初仕事が宇宙だったなんて、すごいなあ…!

『ヴァンガード1号』と名づけられたその人工衛星は、
なんと6年以上も宇宙空間で活動することに成功したんじゃ。
前年の1957年に打ち上げられた人工衛星がたったの3週間で電池切れしてしまったのを考えると、
太陽電池が当時の宇宙研究にどれだけ大きな進歩をもたらしたかが分かるじゃろう。

太陽電池って、世紀の大発明だったんだね。

ちなみに、日本ではいつ頃太陽電池の研究が始まったの?

日本初の太陽電池が発明されたのは、アメリカの発明からちょうど1年後の1955年じゃ。

日本も結構早くから研究開発に取り掛かっていたんだね!

ただ、これはアメリカにも日本にも言えたことなんじゃが、
当時の太陽電池はサイズも大きく製造コストも決して安くはなかったから、宇宙研究などよっぽどのことでない限りは、
実用化はまだまだ厳しかったそうじゃ。
太陽光発電普及のきっかけは「オイルショック」?
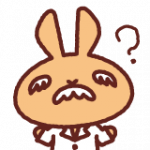
一般的な普及はしばらくの間難しいとされてきた太陽光発電じゃが、思いもよらない騒動がきっかけとなり、普及への道のりを歩むことになるんじゃよ。
さて、ここでお2人さんに問題じゃ。
1970年代に2度起こり、日本ではトイレットペーパーの買い占めなどが問題となった世界的な経済混乱は、通称何と言うじゃろうか?

ええ~っ地球生まれじゃないから分からないよ!

光太君ったら、地球のことも勉強しておかないと!答えは「オイルショック」でしょ?

ピンポンピンポン!その通り、正解はオイルショックじゃ。
当時は多くの国が混乱状態に陥ったそうじゃが、
中でも日本は国内で使う石油燃料のほとんどを輸入に頼っていたから、
オイルショックによる経済面への打撃は相当なものだったそうじゃ。
そしてこのことを教訓として、石油や石炭のような「限りある資源」ではなく、太陽光や風力、水力のような「再生可能エネルギー」の重要性が問われるようになったんじゃよ。
「サンシャイン計画」って何?

1974年に起こった一度目のオイルショックから一年後、
政府は「サンシャイン計画」という政策を打ち出したんじゃ。

(お日様の下でピクニックする計画かな…)

お日様の下でピクニックする計画じゃないからね。

うっ…!じゃあ、一体どんな計画なの?

サンシャイン計画では、「環境やエネルギーにまつわる課題を抜本から見直し、解決すること」
が目標として掲げられ、それを達成するべく策定から1992年までの間に、
なんと約4400億円もの資金が投じられたんじゃ。

物凄い大金…!でも、それだけ力を入れた計画だったってことだね。

そういうことじゃな。
計画や資金の後押しもあって、再生可能エネルギー分野はついにシステム実用化への道を本格的に歩んでいくことになるんじゃ。
エネルギー消費量を減らすための「省エネルギー」という言葉が生まれたのも、この頃と言われておる。
太陽光発電システムはこうして普及した!
住宅用太陽光発電システムが初めて販売されたのはいつ?

サンシャイン計画策定以降は太陽光発電システムの研究開発も進んだんじゃが、
それでも機能面にしろ価格面にしろ、一般的な住宅に導入できる代物はまだ無かったんじゃ。
しかし、それが1992年になると、太陽光発電システムを取り巻く環境が一気に変わったんじゃよ。
そのきっかけは、「ニューサンシャイン計画」の策定じゃ。

“ニュー”ってことは、今までのサンシャイン計画とは違うってこと?

全く違うわけではないんじゃが、「エネルギーの自給自足及び供給源の確保」が主な目標だったサンシャイン計画に、
「環境を保護する」という目標をプラスしたものがニューサンシャイン計画と考えると、分かりやすいかもしれんな。
そして、この環境保護という側面が生まれたからこそ、多くの人々が再生可能エネルギーに注目するようになったんじゃ。

たしかに、専門的な人たち以外からすれば、「エネルギーの自給自足」よりも「環境のため」
だと考えた方が、再生可能エネルギーをより身近に感じられるかも!

そんな時代の追い風を受けて、いよいよ1993年には、
待望の住宅用太陽光発電システムが登場するんじゃ。

ついにきたー!

しかし、そうは言っても当時の住宅用システムはまだまだ高額で、
一般的な家庭に設置する際の平均容量である4kWの場合は、なんと 1500万円前後は必要になると言われていたんじゃよ。

た、たっかーい!

とてもじゃないけど「よし、やってみよう!」とチャレンジできる価格ではないね…

1994年には一応補助金制度も生まれたんじゃが、
それでもよほど環境問題への興味や関心が無ければ、積極的に導入するケースは多くなかったそうじゃ。
太陽光発電システムのこれから

普及当初こそ売電による収益目的の導入が多かったものの、
最近では本来の目的通り「環境メリット」重視の家庭もあれば、
「災害対策」として住宅用システムを設置する家庭も増えているみたいなんじゃ。
ここ十数年の間に進行した地球温暖化や発生した自然災害を受けて、人々の意識が確実に変わってきていることが分かるのう。

いわゆる「インフルエンサー」と呼ばれる有名人たちが環境問題に取り組んでいるのも、よく話題になっているしね。

その影響もあるのかもしれないね!

そうかもしれんな!いずれにせよ、次世代、次々世代の子どもたちが安心して暮らせる環境を作るためにも、
太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの普及は、これからも進めていく必要があると言えるじゃろう。
博士のまとめ

開発以降、安定した設置率を誇り続けていると思われがちな太陽光発電システムじゃが、
普及までの道のりは決して楽ではなかったということが、お分かりいただけたじゃろうか?
今までの歴史を踏まえた上で、これからも太陽光発電システムは、
省エネ社会を引っ張っていく重要な存在であり続けることじゃろう。